帝国ルート後のフェリクスとイングリットのペアエンドについて、強めの幻覚で妄想を膨らませています。
剣を捧ぐ 1
およそ5年に渡る戦乱は、アドラステア帝国がフォドラ全土を統一し、幕を下ろした。
◇
勝利の宴の最中、誰に何を言うわけでもなく去ろうとしている1人の剣士がいる。
「フェリクス!あなた何処に行くの!?」
「……。」
「フェリクス!」
引き留めるのはイングリットだ。
「これからが大切な時よ。ファーガスやフラルダリウスの民がどうなってもいいの?」
「…どうなってもいい訳ではない。適任がいるというだけの話だ。」
「そんな無責任な…。」
「無責任だ?俺なんぞ戻ったところでどうなる。俺は親父殿を斬った。あの王も……友も…。そんなやつがファーガスの民に受け入れてもらえると思うか。だからこそ皇帝やら先生やらに任せておけばいい。」
「フェリクス…!」
◇
フェリクスは使い込んだ銀の剣だけを携えて、傭兵として生きることを選択した。荒廃した各地では、小さな争いやいざこざが絶えなかった。そう、まだ剣を必要とする場所があったのだ。強くなること以外に定めるべき目標はなく、彼は自然にその道を歩んでいた。
そして彼のそばには何故かソシアルナイト、イングリットの姿があった。
フェリクスは女連れでは面倒だと何度も追い返そうとしたが、「馬に乗れたほうが便利でしょう?」と乗馬の指南役を買って出たり、「交渉事はあまり好きではないでしょう。」と雇い主との折衝を請け負ってくれたりするのを断りきれずにいるうちに、ずるずると、気がつけば数カ月を共に過ごしていた。
俺自身は選んだ道だ、後悔はない。ただ、彼女はどうなのだ…?こんな人生が幸せなのかどうか…。
彼は彼女の心の内を計りかねていた。騎士になるか、親の勧めで結婚するかを悩んでいた幼馴染が、他の幼馴染ふたりを殺した自分に、何故ついてきて、何故立つ必要もない戦場に赴き、返り血を浴びているのか。
何故?
付いてくるなと言うことはできるのに、その理由を問えずにいるのである。
考える度、心臓が締め付けられるように苦しくなる。不安、焦り、戸惑い、憤り…、様々な感情がドロドロに溶けたようなが黒いもやが胸の中に渦巻いているようだった。
それが理由なのかは定かではないが、たまに街で酒を嗜むと、少しだけ饒舌になったフェリクスが、少しだけ大きな声でこんなことを言ったりする。
「お前は騎士には向かん。だが傭兵にはもっと向かん。早くガラテアへ帰れ。」
好きな食事を楽しみ、機嫌がよさそうなイングリットは、こう返す。
「傭兵って言ったって、ただの人助けよ。お金になればなんでもやるという訳ではないし、実際あなたが選ぶ仕事だって、人道から外れたようなものは1つもないわ。」
「阿呆か。折衝はお前がしているだろう。」
「あら。仕事を選んでくるのはあなたじゃない。それに私がいなければ、本当にどんな仕事でも請けるのかしら。」
「チッ…。早く嫁にでも行ってしまえ。」
そしていつも筋書き通り、最後にはフェリクスが二の句を継げなくなり、イングリットは上機嫌で、街の宿屋に戻ったらそれぞれの部屋で休むのである。
◇
2人で馬を駆り各地を放浪する中で、野営をすることも度々あった。イングリットは貧しかったとはいえ貴族出身であり尚且つ女性だが、帝国軍に身を置く中で多くの戦場を経験していたこともあり、野営を厭うそぶりは見せなかった。
その日は気候の変わり目で、日中、急に日差しが強くなり気温が上がっていた。暑さをしのぐ為に森の中の街道にルートを替えたが、そのせいで時間がかかり、予定していた街に着く前に日が暮れ始めた。森の中は既に薄暗くなり、少し開けた場所にでたところで、空に残る夕陽を頼りに野営の準備に取り掛かることになった。
「ごめんなさい。私が森の街道を勧めたから、街まで行けなかったわね。」
馬を降りたイングリットが言う。
「構わん。お前の言う通り、あの日差しの下を走っていたら、馬がへばっていた。どの道、今日はこうなっていた。」
簡素な天幕をはりながら、フェリクスが返す。武具をおろし天幕横に置くと、2人は慣れたもので、言葉を交わすことなく支度をしていく。
フェリクスが焚き木を拾い火をおこし、その間にイングリットが二頭の馬を撫でて労い、水を与える。イングリットが塩漬け肉をつかってスープを作り、フェリクスは馬具と武具を点検し、地図を広げて行き先を確認する。料理の頃合いを見て、2人は火を囲んで座った。もうすっかり日も落ちて、星が輝き始めていた。
焚き火の音がパチリと響く。日中のうだる暑さはもうすでになく、たまに吹く夜風が心地よかった。
2人は何も話さないことも多かった。幼馴染の2人だが、いや、幼馴染の2人だからこそ、いろんなことを思い出話にするには、まだ日が浅すぎた。
スープに口をつけた途端、珍しくフェリクスが口を開いた。
「うまいな。」
反射的にイングリットが彼を見上げる。バツが悪そうに皺を寄せた眉間に右手を当てている。
「…感想を言っただけだ。」
お前を褒めたわけではないと言いたげな態度に、イングリットは思わず笑ってしまう。
「ふふっ。ありがとう。」
照れ隠しなのかフェリクスの舌打ちが聞こえる。
「この間の街でね、新しい香辛料を手に入れたの。あなたの好みかなと思って。口にあったみたいで、よかったわ。」
それ以外会話も特になく、パチリと焚き火の音がするだけ。
食べ終わった頃、どちらからということなく、ふと見上げると。枝葉に囲まれた夜空の中に、満月が浮かんでいた。
「…ファーガスにも。この月は登っているだろうか…。」
満月を見つめたまま、フェリクスがつぶやく。その表情は苦しげで、まるで泣いているようであった。
雲ひとつない夜空に蒼く輝く月。月色の髪のかつての主君を想っているに違いない。その主君を守って散った兄を、死ぬときは一緒だと約束した友を、ファーガスの盾と呼ばれた父を想っているに違いない。
フェリクスはそのうち3人を、先の戦争で躊躇いも見せずに斬った。心の内は誰にもわからない。しかし、斬りたかったわけではないことは、イングリットにも痛いほどわかる。そんな彼に、月の光は今の彼には眩しすぎることも。
「そうね…。」
パチリ…。
焚き火の音だけが響く。
彼は自分の両手を開き、手のひらを見つめる。炎が両手を照らし、影を作り、手のひらの上で朱色と影がユラユラと揺れている。
「…お前はもう、休め。明日は暑くなる前に動く。」
フェリクスはそういうと天幕を見やり、イングリットに入るよう促した。
「ねえ。今日は疲れてるようだし、あなたも天幕で休んだら…。」
「…気が向いたらな。」
フェリクスはいつも、天幕に入らない。外で異変があれば、真っ先に自分が剣を抜くつもりでいるらしい。
イングリットは促されるまま天幕に入るが、今夜の彼の様子が気になって心がざわついていた。いつも強がって不遜な態度を取りがちだが、本当はとても繊細なことこ彼女は知っている。
天幕の端を少し開けて、フェリクスが見える位置で眠りについた。
◇
真夜中だろうか。俺は目を覚ました。火を落とした森の中は暗かったが、木々の間から月光が漏れさして、ぼんやりと辺りを照らしている。
濃い気配を感じ、上体を起こして、目を細める。
ゆらり。
真正面、遠くに、蒼い影が小さく浮かぶ。蒼い影は徐々に大きくなり、俺に近づいてくるのがわかった。どんどん濃くなるこの気配、尋常ではない殺気だった。この妄執の気配を、俺は知っている。
「ディミトリ…!」
傍に置いていた剣の柄に手をかける。
刹那、俺は左右から別の気配を感じる。
右の叢から、激しい情念を纏った紅い影が。幼かったかつての俺が、憧れを抱いた…
「シルヴァンッ…!!」
左の暗がりから、懐かしくも厳しい黒い影が。
「親父…殿…!」
3人はジリジリと俺に近づいてくる。手前からは仕えるはずだった王、右からは一緒に死ぬはずだった友、左からは国を愛し王に最後まで仕えた父。
俺は、剣の柄にかけた手を下ろした。ああ、そうだ。戦争は終わった。俺の役目は終わりだ。守りたいものも守れたはずだ。彼らの手にかかり、ここで朽ちるのも悪くない。
3人はついに俺の目の前に立った。無表情だが眼光は鋭く、ジワリと得物を握り直し、構える。
詫びるのも違う気がした。俺は俺の信念を果たしたまで。
目を閉じて、その時を、待った。
得物が振り下ろされる音を聞くと同時に、体表に温かさを感じるーーーーー
それは、湧き出る血液、
ではなかった……。
◇
目を開けたフェリクスは右手を腹部に手を当て、流血がないことを確認し、そのまま顔の前に持ってきた。濡れてないし痛みもなく、傷ひとつない。
「…死なな、かったか?」
左腕は動かない。暖かく、重たいのだ。腕を動かそうとして、自分が仰向けの状態であることに気づいた。重たい左半身を確認しようと右手を動かして弄ろうとする。サラリとしたものに触れ、やっとわかった。これは、髪の毛だ。
「……イン、グリット…?」
髪を少しだけ梳いたあとの右手が、所在無げに漂う。イングリットはフェリクスの左半身にしがみついていた。
「泣いて、いるのか?」
少し震えている。フェリクスの右手は、少し躊躇ってからそっと彼女の頭に触れる。イングリットはわずかに身を強張らせてから、そっと顔を上げた。悲しみに歪んだ顔。涙の跡。目が合うと、彼女はゆっくりとフェリクスの頬に触れた。
「私じゃなく、あなたが…」
そういって親指の腹でフェリクスの目尻を拭った。その感覚で、彼は自分が涙を流していたことを知った。そしてあの蒼い影は、妄執は、夢だったことをやっと悟った。
「そうか…。」
フェリクスはもう一度目を閉じる。
「夢か…。」
イングリットはもう一度フェリクスに顔を埋める。あれだけ激しく脈打っていた心臓が、徐々に凪いでいくのを感じた。
「…あのままだと、俺は。かつて斬った猪達に、刺し殺されていた。」
そうして今度は、些かぎこちない手つきでイングリットの頭を撫でる。イングリットはしがみついたまま、フェリクスに顔を擦り付けるように首を横に振る。そのままの状態で、状況を話し出す。
「…あなたが、とても苦しそうに泣きながら呻いてたから。どんな夢かはわからないけれど、誰の夢かはわかったから。」
堰を切ったように言葉が溢れてくる。
「私、どうしても放っておけなくて、起こそうとして、声をかけたり、軽く肩をゆすったりしたのだけど、全くあなたに届かなくて。それで私、あなたに…」
しがみついて揺さぶっていたのだけれど…と、イングリットはそこまで言うと、我に返った。抱きついているような状況であることに、急に気が付いたのだ。
「ご、ごめんなさい!私!」
なんだか恥ずかしくなり咄嗟にフェリクスから離れようとする。フェリクスは反射的に彼女を抱き止めた。そしてそんな行動をした自分に驚いていた。イングリットも何が起きたか即座に理解できずにいた。
二人とも、今つむぐべき言葉を見つけられないでいる。抱きしめて、抱きしめられている、それだけの時が過ぎる。月は傾き森の影に隠れ、今はもう見えない。しんとした森の静けさのせいで、否が応でも、凪いでいた互いの鼓動が早まっていくのを感じる。
フェリクスは、己が心の奥底を初めて理解した。何故自分についてくるのか訊けずにいたのは、その答えが怖かったからだ。そしてその答えの続きには、必ず何故そばにいることを許すのかを明かさねばならなかったからだ。
騎士になんてなって欲しくない。誰かに仕えて死ぬくらいならば、どこかに嫁に行ってしまえばいい。お前が笑って生きてくれさえすれば…。
それだけだった。イングリットを抱く腕に、少し力がこもる。自分でも、自分の鼓動が煩い。もう、気持ちが隠せない。後戻りはできない。
フェリクスは内心、自嘲した。こんな時あの色情魔ならどう言うか、なんて柄にもないことがよぎったからだ。つい今しがたあんな夢を見たばかりだというのに、と。
満月に唆されて、狼になりそうな自分をできる限り押さえる。
でも、どうせ後戻りできないのなら。もう、どうなったって構うものか。
渇いた声を絞り、フェリクスが語る。
「夢の中で、俺は、俺が斬った3人に、斬り殺されるところだった。」
腕の中のイングリットが、彼の服をキュッと握った。
「俺は死んでもいい、と思った。戦争は終わった、役割も終わった。」
「フェリクス…」
フェリクスは身体を起こし、自分の方を向いて座るイングリットの両肩に再度手を置いた。至近距離で、目が合った。
「守りたいものは、守れたから。」
「守りたい、もの?」
フェリクスは、緊張して、彼女を見つめたまま。
「…お前だ、イングリット。俺は、ずっと、お前を。お前だけを守りたかった。」
身体は密着していないのに、肩に置かれた両の掌から、フェリクスの鼓動がどんどん早まるのが伝わってきた。イングリットは、幼馴染の初めて見せる表情に驚いた。その熱を孕んだ優しい眼差しに、彼女は胸がいっぱいになる。自分の口元を押さえ言葉を探すが、先に涙が溢れてきて、恥ずかしさから俯いて目をそらしてしまう。
自分が何故、傭兵となった彼を追ってきたのか。彼女もまた気づいた。幼馴染が心配だったから、ではなかった。いつの頃からか、ずっと好きだったのだ。
フェリクスは俯く彼女を少し引き寄せて、左手で彼女の腰を抱き、右手で彼女を顎を上げた。熱を帯びた眼差しのまま、問いかける。
「…俺で、いいか?」
イングリットは溢れる涙を止めることができない。震えそうな声で、精一杯応える。
「あなたが…あなたが…いい…」
2人はどちらともなく自然に唇を重ねた。軽く触れるだけで、熱くて柔らかい感触に、脳が蕩ける。
ゆっくり角度を変えて、何度も、何度も、柔らかく触れる口付けをしながら、フェリクスはゆっくりと優しくイングリットを押し倒していく。彼女の上に覆いかぶさり、唇、頬、耳に口付けて、ようやく顔を離した。イングリットは少し苦しそうに、艶のある吐息をほんの少し漏らした。
くらくらした頭でも、残っている理性の所為で、見つめ合うとやはり少し気恥ずかしい。それでもフェリクスの瞳に宿る熱は消えずにいて、イングリットは目をそらすことができず、心臓が破裂しそうなまでに高鳴っていた。
浅い呼吸を繰り返していたフェリクスが、空を見やり2度深呼吸をしてから。 再びイングリットを見つめる。
「一度しか言わん。」
もう一息吸って、
「好きだ。俺の剣、生涯、お前に捧げる。」
イングリットがはにかむように唇を噛んでから、
「はい…。」
そのあとの言葉は、火傷するほど熱い唇に遮られ、声にならなかった。
◇
あれから幾つかの戦場を渡り、幾つかのかの季節を過ごした。彼は少し、いや大分変わった。相変わらず不愛想なところもあるけれど、心から私を慈しんでくれる。
大きな街に立ち寄った時に、彼の誕生石をあしらった指輪を贈ってくれた。彼は私の誕生石を入れた指輪を嵌めている。一度しか言わないと宣していた言葉も、結局は何度も、何度も言ってくれる。笑ってしまうほど、想像と違う。大切にして貰えているのだと、日々感じている。
今、私たちは小さな湖のほとりの、小さな町についたところだ。本当はもう少し先の町まで行く予定だったのだけれど、なぜかフェリクスが早めに休もうといって宿をとったのだ。
「ねえ、フェリクス。どうしたの?」
通された部屋の窓際で、荷物を整理しながら私は彼に訊く。
「……。」
昔からの不愛想か、単に聞こえなかったか……。
「フェリクス?」
彼は私の方をみて、それから近づいてきた。私の両肩に手を置き、言葉を選んでいるそぶりを見せる。
「お前、…具合が悪いのではないか?」
「え…?」
思えば確かにここ数日あまり食欲もなく、馬上でも少し酔うような感覚があった、ような。
「そう、かしら…」
自信なさげに相槌を打つ。
「まぁ、そうでないならそれが一番いい。」
彼は俯き加減でふぅーっと長いため息をついたかと思うと、今度は両拳を天井に持ち上げて伸び上がった。
「急ぐ約束があるわけでも、路銀に困っているわけでもない。それに見ろ、いい長めじゃないか。」
促されて窓の外を眺めると、どことなく故郷にも似た雰囲気のある美しい湖畔だった。
「綺麗ね。」
「だろう?俺も少し疲れている。こんな景色の良い町で、俺も少し休みたい。」
心配してくれているのが分かった。相変わらず嘘がつけないのだなあと、なんだか嬉しくなった。
「そうだ。そういえば腕のいい鍛冶屋がいると、前の街で聞いたな。後で行ってみるか。」
町の市場に立ち寄ると、小さい町ながらもいろんな物品が流通していた。本を扱う商人も立ち寄るようで、彼は数冊買い込んで、私にも何か選ばないかと声をかける。物語と料理の本を選んだ。彼は少し可笑しそうにしていたが、厭味な感じはなかった。
噂の鍛冶屋にも行ってみる。腕がいいというのは本当だったようで、フェリクスは職人と意気投合し、剣について語り合っていた。
昔と比べたら、彼は良く喋るようになった。士官学校や戦争の時代や、グレンが生きていた頃よりも。人との関わりを敢えて避けることもあまりなくなり、笑顔も優しくなった。物腰も…少しロドリグ様に似てきたと思う。
そのまま町の料理屋で夕食にする。私はやはりあまり食べたい気持ちにならず、注文したものの殆どはフェリクスが食べることになった。
「小さいがいい町だな。」
「そうね。」
「…しばらく居てもいいかもな。あの鍛冶屋の親父ともう少し話してみたい。」
「あら、ご執心ね。」
「なんだ?妬くか?」
ニヤリと口角をあげながら、顎を上げて自慢げな表情をする。
「うふふ、そうね。」
私は、こんな暮らしが続くのも悪くないかもしれない、と思った。すっかり暗くなった宿までの帰り道、月明かりが私達を照らし、影を作る。
「…満月か。」
月を見上げるフェリクスの顔は、とても穏やかで優しかった。幾節も前に月を見て苦しんだ彼を、彼は乗り越えていた。
その日の夜、私は不思議な夢を見た。
かつての先生のような翡翠色の髪を持つ美しい人が現れて、口付けて微笑んだ。
私のお腹に。
「おめでとう。」
誰の声かはっきりとわからなかった。でも、おめでとう、と聞こえた。
はっとして目が醒めた。
体を起こして辺りを見る。
フェリクスは隣で眠っている。
窓の外はまだ夜で、湖面に月が揺らめいていた。
私は自分のお腹に手を当てる。
ただの、夢?
本当に?
そういえば月のものがほんの少し、遅れているような気もする。私の心臓が徐々に強く、最後には飛び出そうなくらい激しく脈打つ。
もしかして、フェリクスは…?
カンのいい彼のことだ。私よりも先に気づいているのかもしれない。
もし本当にそうだとしたら、少しだけ悔しい。
私が起きている気配に気付いたようで、フェリクスが目を開ける。
「どうした、眠れないのか。」
彼は上体を起こして座り、私が掌をお当てているお腹に視線を移した。
まだ言うべきではないのかもしれない。
でも、今日は満月。月はいつだって、私達を導いてきた。
「…夢を見たの。」
「夢?」
「誰だかわからなけれど、綺麗な人がでてきてね。お腹に口付けてくれて。
…それから、誰かが、おめでとうって言ってくれた。」
フェリクスは目を見開いて、束の間絶句して、息を飲んで。
「…そうか。」
といって、私を抱きしめた。
「ふふっ、夢の話よ。」
「ああ、そうだな。だが、天啓かもしれんぞ。」
ただの夢で終わってしまったときのために、
重圧をかけないよう気遣ってくれるように思う。
でも、声色がなんだか上ずって、嬉しそうだ。
「……俺は、それが、天啓でも構わん。」
抱きしめる腕に力がこもった。
「俺にどんな生き方ができるか、まだわからない。
だが、俺の剣は、この先も、生涯お前に捧げる。」
もしそうなったら、戦いを捨てることも考えていると、
私は初めて知った。予想だにしていなかった。
この人はいつも私の胸をいっぱいにさせる。
愛おしいという感情が私の中に収まりきらず、弾けてしまいそうだ。
私は昔、騎士に憧れていた。
私は今、憧れていたままの騎士に、守られてる。







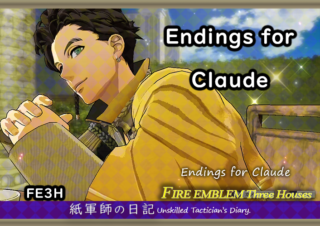
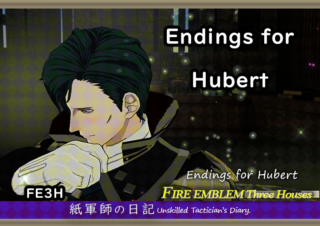
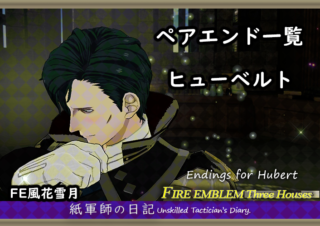




コメント