※約5500文字です。
※銀雪ルート、ペアエンドの妄想です。
※ネタバレを多分に含みます。
◆◆◆◆
セテスの口付けはいつも、触れるだけの、浅く、短い口付けだったーーーー……
終戦後、フォドラ統一王国の国王となったベレスには休む間もなかった。それは、ともに戦ってきた教え子たちや、政務を補佐してくれるセテスも同様だった。今もかつての名残で「枢機卿の間」と呼ばれる部屋で、朝から晩まで膝を突き合わせて議論し、新たな時代を創る礎を整えていた。
その日は終戦後最初の日曜だった。ベレスは残る議題の書類の束をみやる。装飾された窓は開け放たれていて、外に目をやると、ほんのり赤く染まっていた。会議に参加している皆の顔色をみたベレスは、少し深く息を吸い込んでから言った。
「……皆、今日はもう帰って休んで。」
「なっ…!陛下…!?」
セテスが慌てて諫めようとする。ベレスは書類を手にまとめ、話を続ける。
「あとは私の決裁の部分だ。明日までに決めておく。明日の朝、続きを話そう。」
ベレスはセテスに視線を送った。皆を少しだけ休ませてやってほしい、と。セテスは眉間にしわを作りながら皆の様子を見、少し考えてから、明日の予定を伝え、皆に休むよう指示を出した。
皆が帰った後の枢機卿の間は、がらんとして、とても静かだった。夕焼けが窓から見える。
「セテス、すまない。ありがとう。」
ベレスが眉を下げながら口を開く。セテスは小さくため息をついて、少し困った顔をして微笑む。
「皆、疲れているようだったものな。……そして君も。」
「そうだね。……でも、まだやるべきことが残っている。このまま、ここで片付けてしまいたい。すまないが何か飲み物を持ってきてもらえないだろうか。テフでも茶でも、なんでもいい。」
セテスはわかったと言い残し、支度をしに行った。
「紅茶をいれてきたぞ。」
枢機卿の間に戻り声をかけるが、返事がない。
「……ベレス?」
ベレスは一番奥の机に、両腕を重ねて頬を置き、眠っているようだ。
陽が刺さないこの部屋にも、燃える夕焼けの色が映りこむ。
「全く……。」
セテスは口元に笑みを浮かべながら、小さく呟いた。彼女の近くまで紅茶を運び、適当なところで机に置く。
ベレスを起こすために肩に手を置こうとしたとき、窓から風がそよそよと吹いた。頬にかかった髪がさらりと後ろに流れ、彼女の美しい顔だちを露わにする。
この美しい人が私の妻なのだ。フォドラが落ち着きを取り戻すまで、公表しないことにしたが、それでも私の妻であるという事実に変わりはない。
実のところ、まだ口付けもしていない。彼女と交わって熱を近くで感じたいと、思わないわけではない。しかし、新しい時代を創るこの瞬間は、それに集中させてやりたい。私たちには時間がある、焦ることはない。セテスはそう思っていた。
だが…。
美しい寝顔に、まるで吸い寄せられるように。
そうなることが自然の摂理であるかのように。
セテスは屈んで、唇を重ねた。
柔らかい熱を感じた刹那、セテスは激しく脈打ちはじめた自分の心臓に驚く。
私は、今、なにを…
慌ててベレス離れ、少し汗ばむ手で、茶の支度を続ける。
ベレスはゆっくりと目を開けて、体を起こした。
「……セテス。今……。」
彼女は指先を唇のあたりに置いた。その仕草に、セテスの鼓動は早まる。
「今、私……寝ていた?」
「……ああ。茶の用意ができたら、起こそうと思っていたんだ。」
「そう……。ありがとう。」
ベレスは、目の前に差し出された温かい紅茶をひと口すすった。
「……なんだか、眠気は覚めた、みたい。」
そう言って書類の束に向かった。
翌朝。
セテスはいつものように、ベレスの部屋に行く。かつてレアが使っていた大修道院三階の部屋に行き、扉を叩き、支度が整ったか声をかけ、その日の予定を伝えるのが日課となっていた。
幸い、昨日のことはベレスも覚えていないようだし、と何食わぬ顔で部屋の扉を叩く。三回叩いて少し待つと、ベレスの声がする。少し眠い、と呟いている。
セテスがふぅとため息を吐いていると、内側から扉が開いた。
「ベレス…。」
「支度はできている。だけど、まだ、少し眠くて。」
ベレスはセテスを見つめ、何かを考えるように顎に手を当てて、首をかしげる。
「ん?……どうした。何か言いたいことがありそうだが。」
ベレスは俯いて、少し迷ったように言葉を紡ぐ。
「少し眠くて。……目が覚めるから、また、してほしいのだけど……。」
「してって、何…を……。」
セテスには一つだけ心当たりがあった。ベレスは俯いたまま顔を上げない。
「……あの時、起きていたのか。すまな…。」
「いいんだ。あの時は寝ていた。だけど、あんなことされたら…目は覚める……。」
セテスの謝罪の言葉は遮られた。ベレスは少しだけ体をよじって、彼女がどんな気持ちだったかを伝えてくる。セテスは急に加速する自分の鼓動を制した。
「……ねえ、もう一度…。」
自分が蒔いた種だ、セテスは余計に頭が痛い。戦後の復興を目指す今は、「そんなこと」をしている時間はない。彼はやれやれと言わんばかりに自分への盛大なため息を吐きながら、辺りを見回す。幸い、急に誰かが通る場所でもない。
セテスはほんの小さな声で、ベレスに囁く。
「一度だけ、だ……。」
そして両手で彼女の頬を優しく覆い、上を向かせ、ほんの一瞬、浅く、短く口付けた。
唇を離し、咳払いをしたセテスは、公で使う声色で訊く。
「……目は覚めたか?」
「大丈夫だ、問題ない。……仕事を始めよう。」
二人は連れだって枢機卿の部屋へ赴く。ほんの少しだけ、ベレスのほうが前を歩く。
セテスは彼女の姿を視界の端に映す。振り払っても、振り払っても、彼女の唇が昨日より熱かったという事実が、頭から離れなかった。
次の日、またその次の日。ベレスは毎日、同じ手法で口付けを要求した。
その度にセテスは、一度だけ、と言って、浅く、短く、口付けた。
気が付けばそれは、まるで病魔のように忍び寄り、心に痛みを刻んでいく。
繰り返せば繰り返すほど、するどい棘が抜けなくなり、欲が出て、もっと欲しくなる。
終戦から一節が経ち、快晴となったある日の早朝。領主となる教え子たちは揃ってガルグ=マクを出立した。大修道院の門の外で、べレスは一人一人に声をかけ、感謝を伝える。教え子たちはその声に勇気づけられ、力強い笑みを浮かべて、それぞれの領地へ向け巣立っていった。朝日に照らされる彼らには、前途洋々という言葉がよく似合っていた。
その光景をセテスは、女神が祝福を与えているようだと思いながら眺めていた。
皆を見送ると、ベレスは振り返り、セテスを見つけて近づいた。
「セテスも。……ありがとう。」
セテスは少し驚いて、
「……陛下も。皆の士気も上がった事でしょう。」
と返し、微笑んだ。
市場を抜け、門番に挨拶をし、中庭を通り、少し静かになった大修道院を二人は歩く。朝の気配が漂う大修道院には、心地よく、優しい風が吹いていた。
「……セテス、お茶にしない?」
皆が旅立ち、「先生」は少し寂しいのだな、とセテスは思った。
「喜んで。国王陛下。」
「久しぶりに私が支度をしよう。」
二人は三階のベレスの部屋へ向かった。
ベレスは扉をあけ、セテスを招き入れる。入ってすぐの場所には、茶会用の家具があった。この部屋を使うことになった折、本人たっての希望で運び入れたものだ。
部屋の中に入るのは、その時以来だな、とセテスは思う。
と同時に、今、入っていいのか、と少し躊躇う。
「さあ、入って。茶の支度をする。座って待っていて。」
結局、促されたまま入室してしまう。
外はまだ朝の凛とした気配が漂っていたというのに、すり硝子のこの部屋は光がぼんやりとして、少し現実味を欠いていた。
ベレスは慣れた手つきで茶の準備をする。生徒たちにもよく淹れてやっていただけのことはある。茶を注いでいくと、豊かな香りが広がった。
「……この香りは。」
「気が付いた?」
ベレスは微笑む。セテスの好む、四種のスパイスティーだ。
「最近、私も気に入っているんだ。冷めないうちに、どうぞ。」
「そうだな、いただこう。」
二人は今後の話をする。自領にもどった彼らはうまくやるだろうか、想定していない問題はどれくらいでてくるだろうか、早馬が飛んでくるのはどこが最初でどんな話だろう。どれもこれも楽しみと不安が入り混じり、まるでこのスパイスティーのようだった。
「いずれにせよ、火急の案件はひと段落した。ベレス。君は数日、少しゆっくりするといい。美味しい茶をありがとう。」
セテスはそういって席を立とうとする。
「ねえ。」
ベレスは呼び止める。
「あの日、いれてくれたお茶、覚えている?」
「……あの日?」
セテスは記憶を辿る。スパイスティー。数週前、枢機卿の間で淹れた茶だ。思い出させたいのは茶のことではないな、と彼は気付く。そこに思い至った様子をベレスはみて、くすっと笑う。それから、こう言って、机に両腕を組んでのせ、頭を伏せた。
「少し、眠いな…。」
彼女を休ませてあげたいから、なにも無いまま、ここを後にするつもりだった。
席を立ち、寝たふりをする彼女に近づき、横顔にかかる細い髪の束を、耳の後ろに掻き上げてやると、少しくすぐったそうに口元に笑みが浮かんだ。
ベレスは笑みを浮かべたまま、セテスの耳になんとか届くくらいの小さな声で、呟く。
「五年くらい、眠ってしまいそうだ……。」
その後すぐ、ベレスはセテスの唇の熱を感じた。
セテスの鍵のかかった理性を揺さぶるには充分な台詞だった。
セテスはいつものように、浅く短い口付けをして、離れ……ようとした。
唇を離した瞬間、今度はベレスが唇を重ねてくる。
セテスが驚いている隙に、何度も、何度も。
熱く濡れた柔らかい唇が、触れて、離れて、触れて、離れて……
セテスは必死の思いでベレスを抱きしめた。彼女の顎を自分の肩に乗せ、抱きとめる。
「ベレス、君は思い違いをしている。」
彼女の少し濡れた吐息が、近くで聞こえる。
「私は、そこまで強くない。……もうこれ以上は、……耐えられなくなる。今、フォドラは君の双肩かかっている。公務に追われない束の間の時間、ゆっくり休んで欲しいんだ。頼む。どうか無理をしないでほしい。」
「……セテス、あなたは思い違いをしている。」
耳元で、くすっと笑う声がする。
「私のこと、ただのフォドラの民だと思っているの?……あなたと同じで、多少丈夫にできている。」
セテスの掌が、しかし、と言いたげに頭を撫でる。
「それから……。私にかかる重圧が心配だというなら、……いい方法がある。」
ベレスはさらりとセテスの掌をかわし、セテスを見つめて言う。
「きっと感じる重さが半分になると思うのだけど……。」
「……半分に?どうやって……。」
ベレスは笑みを浮かべたかと思うと、もう一度セテスの耳元に唇を寄せて囁く。
「あなたと私が、一つになればいい。少しも離れないように、完全に重なって。」
セテスは不意にベレスを横抱きにして立ち上がり、部屋の奥へ進む。
この部屋は奥へ進めば進むほど、すりガラスから差し込む光が強くなる。
ベレスを寝台に降ろすと、自分は寝台のわきに座り込み、ベレスをのぞき込む。
「……ベレス。私は今、どんな顔をしている?」
ベレスは柔らかい光を浴びるセテスの顔をよく眺める。なんだか少し恥ずかしくなってくる。
「わ、わからない……。」
「思ったまま言ってごらん。」
「……ちょっと困ってる顔。」
「それから?」
「……少し意地悪な顔。」
「はは……、それから?」
「……。」
ベレスは口を噤む。物欲しそうな顔、なんて、とても言えなかった。
セテスは微笑んで、顔を近づけて、浅く短く口付ける。
「ベレス……。多分、君も、同じ顔をしている……。」
ベレスは、自分の頬が紅潮するのを感じた。
セテスは彼女の履物を脱がせながらつぶやく。
「私がどれだけ自分を抑えていたか、何度、我慢したか……。」
足のつま先から、足、腰、と指先でなぞり上げていく。ベレスは少しだけ体をよじらせて、セテスの方を向く。セテスは、なぞり上げる指先がベレスの唇まで来ると、唇に着くか離れるかの距離で指先を止めた。ベレスは目を瞑り、耐えている。
「私は何度も止めた。だが、君が望んだ。」
ベレスの吐息が漏れる。
「君にこんなに煽られて、私も、もう余裕がないんだ。恐らく、優しくしてやれない。」
ベレスは胸が苦しくて声を発することができず、代わりにセテスの指を甘く食んだ。
甘く食むと、セテスの唇が下りてくる。
言葉とは裏腹に、真綿のように優しい口付け。
それは、徐々に、徐々に、深くなって、暖かな太陽の光に包まれる中、二人は一つになった。






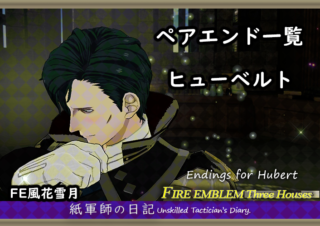

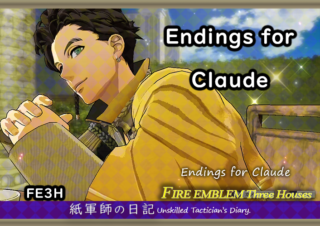

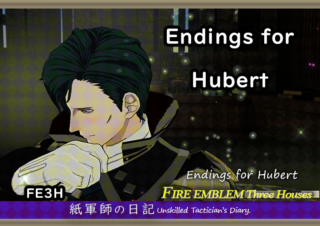



コメント