青い掟
2022/12/18 刻印の誇り17で頒布された合同誌『color』に寄稿した小説『青い掟』をweb公開します。※合同誌『color』は完売しています
聖戦の系譜 フィン×アイラのお話です
約15000字。 目安時間:30分程度。
青い掟
ジェノア城を守っていたのは、美しく舞うように斬る剣士だった。その剣士が跳んだかと思うと、縦横無尽に剣が降り、腰より長く伸びた黒髪が素直に地面に向かう頃には、敵は瀕死であった。
攻めあぐねるシグルドに、キュアンは言った。
「シグルド、あの剣士はイザークの出身かもしれない。黒髪で、あの剣技。おそらく間違いない。ただ、なぜヴェルダンにあれほどの使い手がいるのかわからない。何か、訳ありだろうか」
シグルドはオイフェを呼び、キュアンと三人で作戦をたてた。それはキュアンと見ならい騎士フィンが機動力を生かしつつ陽動、剣士をひきつけ、その間に残りの兵でジェノア城を落とす、というものだった。
オイフェが味方の陣営に作戦を伝達する。その間、キュアンはフィンと作戦詳細を詰めていた。
「……という形が理想的だ」
「はい、承知しました」
「……フィン、あの剣士は相当の手練れだ。少しの油断が命取りになるかもしれない」
「覚悟はできています。見習いとはいえレンスターの騎士。主命とあらば全力でお供いたします」
「そうか。……作戦開始まで時間がある。いい機会だ、得物の扱いを教えてやろう。フィン、槍をとれ!」
「はい!」
作戦伝達が終わると、シグルドの軍は二手に分かれて行動を開始した。
キュアンとフィンは並走し、周りの敵を倒しながら剣士に陽動をかける。味方が倒れていくのを見て、剣士が陽動に乗った。キュアンたちはうまく森に入りながら、剣士の猛追を付かず離れずのところでかわし、ジェノア城から距離をとっていく。
行く手、ジェノア城の反対方向、少し遠いが何か気配がする。フィンが目を凝らすと、すぐ正面にアクスファイターの一群が見えた。
「キュアン様!前方に敵の影が!」
二人が手綱を引き、ジェノア城のほうに少しだけ引き返そうとしたその時。
「はああっ!」
キュアンに向かって剣が振り下ろされようとていた。
「キュアン様!」
振り下ろされた剣がキュアンに届く前に、フィンが槍で牽制。剣士はくるりと身を翻し、すかさずフィンめがけて、猛スピードで間合いを詰めてきた。
森に身を寄せている間に、あの剣士が追いついてきたのだ。フィンは距離をとって躱しつつ牽制、何度目かの一太刀を槍の柄でかろうじて受け流した。遠くで見ていた時より小柄な剣士だったが、流星のように降り続ける剣筋をさばくのが精いっぱいで攻め返せない。
剣舞のような猛攻は、迫り合って一旦止まり、視線が絡んだ。同じくらいの年の少女だった。フィンをきつく睨んでいる。その瞳は深い、太陽の光が届かないほど深い、海の底のような色だった。
じりじりと地面を擦る足音、一陣の風が吹いて砂煙が立つ。
その時。
周囲にいたジェノアの兵が叫んだ。
「し、城が落ちたー!」
フィンが反応するより早く、剣士の瞳に焦りの色が浮かび、刹那、迫り合っていたフィンの槍を突き放して踵を返し、ジェノア方向へ走り去った。
任務を終えたキュアンの顔は晴れやかだった。対してフィンは、思いつめたような剣士の瞳が忘れられず、ただただジェノアのほうを見やっていた。
これが二人の出会いだった。
◆◆◆
ジェノア城が落ち、一人の少年が救出された。名をシャナンといい、イザーク王の嫡男であった。剣士はアイラといった。イザーク王の妹であった。今この時、グランベルと敵対するイザークの王子を救出するという奇妙な出来事。「君の信頼を裏切るようなことはしない」。シグルドの説得を受け入れたアイラは、行動を共にすることとなった。
◆◆◆
ジェノア城を落としたシグルド一行は、そのままマーファ城へ向かう。前線を別部隊にまかせ、キュアンは騎馬の速度を落とし、アイラに話しかける。
「君がアイラ王女、先ほどはすまなかった。私はレンスターのキュアンだ」
「キュアン殿……。あの場では敵同士だった。当然のことだ」
アイラには先ほどの鬼気迫る表情は無く、安堵か不安か、少し肩を落としているようにも見えた。
「イザークの剣士であると思っていたが、マナナン王のご息女であったとは」
「父をご存じなのか?」
「わが父から、立派な方だと聞かされていた。マリクル王子もまた、優れた若者だと」
「そうか……、嬉しいことだな」
少し離れたところから、フィンは二人を見守っていた。少し驚いたり、熱弁をふるうような様子が見て取れた。そして、何やら二人は何やら納得したように、うなずいているようだった。キュアンが何かを思いついたように、あたりを見回していた。フィンと目が合った。
「フィン!」
そう呼んで視線の先の従者を手招きする。思いがけない展開に、フィンは慌てて馬を駆る。
「いかがなさいましたか、キュアン様」
急くフィンを、キュアンは笑顔でいなす。
「アイラ王女、これが我がレンスターの騎士、フィンだ」
「キュアン様!?私はまだ見習いで!」
「騎士にかわりはあるまい?」
「キュアン様!」
ははっとキュアンは笑った。アイラはきょとんとした後、少し笑みを浮かべた。
「フィンは私より歳も近いだろう。私に言いにくいことがあれば、フィンに言ってくれ。私の妻エスリンでもいいんだがな、今少し忙しそうだ。また後で紹介しよう」
「キュアン殿、感謝する……」
キュアンは力強い笑顔で軽く頷き、前線へ馬を走らせた。
「あっ!」
まさか置いて行かれると思っていなかったフィンから、思わず声が出た。アイラからも少し笑い声がもれて、口元の笑みも深くなった。
「キュアン殿は、素晴らしい方だな」
さらりと言った。それがフィンにはとても嬉しかった。
「はい、とても」
◆◆◆
そのままマーファ城、ヴェルダン城を制圧。本来の目的を達成するため、シグルドたちは結果的にヴェルダンの全領土を制圧した。バーハラからの命令により、シグルドはエバンスの城主に任命され、グランベルの国境の一角を守ることとなった。
国境の先はアグストリア。緊張による均衡、束の間の平和が訪れていた。
◆◆◆
エバンス城で過ごす兵士たちは、それぞれ日々鍛錬を怠らなかった。同じ武器を扱う者同士で基礎の確認、模擬戦、あるいは闘技場で腕を磨く者もいた。
その中には、イザークのアイラとシャナンもいた。アイラはシャナンによく稽古をつけた。未来のイザーク王に、その剣技を伝えているのだ。シャナンの動きはすでにアイラのそれを見ているようで、幼いながらも剣聖オードの直系であることを強く感じさせた。
二人の訓練には、シグルド軍の若き軍師オイフェもよく参加していた。シャナンはオイフェに良く懐いて軽口をたたきあう姿もあり、さながら兄弟のように見えていた。
フィンは騎馬兵同士の訓練の後、その三人が稽古をしている場面によく遭遇した。何度も何度も通るうち、気が付いたことがある。それは、アイラが最初のころに比べて、笑うようになったということ。控えめだけど、嬉しそうだったり楽しそうだったり、そんな顔を見かけることが増えた気がする。そんなことを考えながら通りがかりに眺めていると、ふとアイラと目が合った。お互い、思わず息をのみ、目を見開く。
「フィン殿!」
オイフェが声をかけてきた。
「もし時間があれば、こちらへお越しください!」
爽やかなその声でフィンは我に返り、三人の傍へ向かった。しゃがみこんだシャナンが少し息を切らしていた。幼いが、眼光には鋭さがあった。まだ敵だったアイラと戦った時のことを思い出す。深く深く、どこまでも深い色の瞳。
「いかがなさいましたか、オイフェ殿」
オイフェはニコッと笑い、ちらりとアイラを見る。アイラは狐につままれたような顔を一瞬見せた後、軽く咳払いをして。
「フィン殿。その……。もし時間が許せば、シャナンと手合わせしてやってくれないだろうか」
思ってもみなかった突然の申し出に、フィンは驚く。アイラは少し困ったような顔で続けた。
「シャナンが、槍との模擬戦をしたいと以前から言っていてな。その……、ここをたまに通りかかるだろう?だから、フィン殿の時間が取れるときに、模擬戦をお願いしたいとシャナンと話していてな」
通りかかるのを知っていたのか。
フィンの心は緩やかに波打った。
「わかりました。準備してきますので、お待ちください」
フィンは訓練用の槍を用意してくる。そのころにはシャナンの呼吸は落ち着いていて、訓練用の剣をとって立ち上がった。今にも攻めかかりそうな気迫だった。
アイラが立ち合いになり、二人に距離をとらせる。
「フィン、行くぞ!」
シャナンが気を吐き、
「はい、いつでも!」
フィンが呼応した。
シャナンの攻撃を槍先でいなす。しかしシャナンの太刀の重さたるや、まるでアイラの剣を受けているようだった。不意にできた隙に、槍を一突き。シャナンは華麗に躱して、突如猛反撃にでた。閃光を放つような剣戟に、フィンは躱しきれず膝をついた。
「……!お見事です」
シャナンはニヤッと笑みを浮かべた後、攻め切った疲労からか、その場でふらりと倒れて眠ってしまった。残った三人は顔を見合わせて笑う。
「……っ!」
笑った拍子にフィンが少し顔を歪めたのを、アイラは見逃さなかった。先ほどの最後の一振りが、脇腹に命中していたようで、訓練服が裂け、少し血が滲んでいた。
「……!今、エスリン様を呼んでくる!」
「アイラ殿、大丈夫。大丈夫ですから。戦時ではありません、大丈夫。休めば治ります」
フィンは、アイラを制止する。物資のこともあるが、なによりエスリン様もお忙しいからと。
「……では、私に手当てをさせてくれないか。こちらからの願いをきいて貰ってケガをさせたままというのは、性に合わない」
すまなそうな顔をするアイラに負けて。
「……わかりました。そういうことでしたら、……お願いいたします」
フィンはその提案を受け入れた。
◆◆◆
アイラとオイフェは、シャナンを部屋に運んだ。そのままオイフェが付き添ってくれる。
アイラは道具を揃え、フィンの部屋に向かった。扉を三回たたく。
「申し訳ありません、わざわざ……」
「いや、これは私たちの落ち度だ。申し訳なかった」
アイラは部屋に入ると、軟膏や清潔な包帯、はさみなどの道具を並べた。
「フィン殿、服を」
「?」
「手当をするから、傷口を見せてくれ」
◇◇◇
私は多分、ほんの少し、動揺したかもしれない。自分の部屋に、彼女と二人きりで。傷口を見せてくれと言われて。動揺というより、ある種の高揚のような、頭に血が上るような感覚。傷口は脇腹で、服をたくし上げてというのも難しい場所だった。
「……わかりました」
私はそう答えて、破れた訓練服を脱いだ。傷口に少し張り付いていた繊維が剥がれて、じわっと痛みが広がった。
「……っ」
傷口自体は大したことはない。かろうじて血が出る程度の、剣先がかすめただけの傷だ。訓練服を簡単にまとめ、そのままベッドに腰を掛けた。
「……やはり薬が必要だな」
傷口を見た彼女はそういって、軟膏を指に取った。剣を振るっていると思えないような、華奢な手のひらが傷口の傍に置かれた。じわっと体が熱くなっていく。今度は彼女のもう片方の手。軟膏を掬った指先が、傷口に触れた。体中に熱い雷が走ったように痺れた。
「沁みるか?すまない」
私が少し動いたので、アイラ殿が心配している。
「いえ、大丈夫です」
そう答えて、ふうっと息を吐き出した。アイラ殿は手際よく、今度は包帯を取り出す。そこまでしなくても、と言ったのだが、
「恩には、報いる。それがイザークの戦士の掟だ」
と返された。細い指先で包帯の端を摘んで、口にくわえた。ピンと伸ばした包帯で傷口を覆うように、胴体に巻いていく。傷口の辺りから、少しずつ。両手の指先が私の体を這うように、包帯を抑えて進む。
彼女から一番遠い部分を巻くときに、私との距離が一番近くなる。髪の毛が素肌に触れた。激しい痛みが体に走る。傷の痛みではない。心臓から送られる、血液の量が、速さが、体を内側から叩いている。顔が、熱い。いや、体中が熱い。一周、二周……。繰り返されるたび、意識がどこかに飛んでいきそうだった。もう限界だと思ったその時、彼女は口にくわえた包帯を外し、最後に巻いた端と結び止めた。
「これで。……よし。……終わったぞ」
見事に巻き付けられた包帯を改めて確認する。触ってみる度、どくんどくんと心臓が音を立てる。
「……ありがとう、ございます」
口の中が渇いているようで、声がうまく出せない気がする。間を嫌がった私は続けた。
「上手いものですね」
「ああ……。昔、兄上のケガも手当てしたりしたからな。割と慣れているんだ」
アイラ殿は手際よく道具を片付けながら、答えてくれる。ああ、帰ってしまうんだな。一瞬、そんな思いが頭をよぎって、はっとする。何を考えているんだ。首を振って落ち着こうとする。彼女は道具をまとめ終えると、あたりを見回し、視線を止めた。視線の先を追うと、ベッドの上の、破れた訓練服にたどり着いた。彼女は進み出る。まさか、訓練服を手に取ろうとしている?縫ってくれるというのか?そこまでしていただく訳には。
私は手を伸ばす。
訓練服を掴んだ。
そして、気が付いた時には、彼女も手を伸ばしていた。
ほんの少し私のほうが早くて、
彼女の手は、私の手の上に。
彼女の手の熱が伝わってくる。指の細さが。あんなに剣を振っているのに、しなやかで柔らかくて。自分とは全く違う質感だった。
「……フィン殿?」
「……服を、着ます」
「破れているだろう、私に縫わせてほしい」
「そこまで手を煩わせるわけには参りません」
「シャナンが破いたものだ」
「私が躱しきれなかっただけですから」
「しかし……」
「……傷の手当を、していただきました」
「それは、当然のことだ。縫うのは、訓練に付き合ってくれた礼だ」
「……」
私は反論が思いつかなくなった。
「恩には報いる。それがイザークの戦士の掟なんだ」
イザークの戦士の掟。強い意思で押し込まれて、私は観念した。とたんに彼女の手がまだ自分に重ねられていることが妙に気恥ずかしくなり、その手は神経質にピクリと動いてしまった。動揺したことを彼女に気づかれたのなら、それもなんだか恥ずかしい。
「……わかりました。では、お願いいたします」
両手で訓練服を持ち上げ、アイラ殿に渡した。
「ああ、任せてくれ。フィン殿」
今まで、どうも違和感があったのだ。その違和感の正体に、私はこの時気づいた。
「アイラ殿。私のことは、どうぞフィンと呼んでください。あなたはイザークの王妹であられるのですから」
彼女は一瞬驚いた顔をして、その後、寂しく笑った。国は今、事実上滅亡したとも言える。そんな中で王妹など、とでも言いたげな表情だった。
「アイラ殿。シャナン王子がいる限り、イザークは。剣聖オードの血は、そこにあります」
気のきいた言葉など浮かばなかった。ただ事実だけを述べた。アイラ殿は、ふぅと息を吐いて、
「ありがとう、……フィン」
そういって、少し笑った。
「キュアン殿が羨ましいな。このように真っ直ぐに具申してくれる者が傍にいる」
「アイラ殿もどうぞ、なんでもお申し付けください。我が主君キュアンも、何かあれば私にと申していたではありませんか」
アイラ殿は訓練服を抱きかかえたまま、片手を顎につけ、考える様子を見せている。
「……必ず解決できるかはわかりません。でも……、例えば、恩に報いるのがイザークの戦士の掟なら、あなたの困りごとを必ず聞いて、できるだけ取り除いて差し上げることが、あなたと私の間の掟、と……」
そこまで言って、気恥ずかしくなり。私は頭をかいた。
「いえ……少し、恰好をつけすぎましたね」
アイラ殿は笑ってくれた。
「ふふ、ありがとう。フィン。では一つ、早速きいてくれないだろうか」
「なんなりと」
「私のことも、どうぞアイラと呼んでほしい」
「それは……」
できかねる。王妹でシャナン王子の後見人でもあるのだ。
「どうした?私たちの掟ではなかったのか?」
降参だった。私では太刀打ちできない。
「わかりました。……アイラ。その……服を、頼みます」
アイラは笑みを深めて言った。
「……ああ、任せろ」
彼女が部屋を出て行った。でもなんとなく彼女の香りが残っているような気がして、私は少しの間、その余韻に浸った。
◆◆◆
エバンス城での束の間の平和は、アグストリアの賢王イムカ暗殺により幕を閉じた。
イムカの長子シャガールと反グランベル派の諸侯が、グランベルが駐留するヴェルダンへの侵攻を始めたのだった。
エバンス城の西には、親友エルトシャンが治めるノディオン王国がある。ヴェルダンでの戦いの最中、シグルドの背中を守ってくれたノディオン王エルトシャンは、今回の戦いについてシャガール王へ意見具申し投獄され、それに乗じてハイライン城の軍がノディオンへの侵攻を開始したという噂が流れた。城には王妹ラケシスがいるはず。シグルドは、彼女を救うために急ぎ進軍した。
シグルド軍の陣容は、騎馬隊や剣士たちが中心だった。騎馬隊が先行、敵を牽制し攻撃を受け流し、後続の剣士がとどめを刺す。その連携がメインの戦術だった。フィンとアイラも例外ではなく、フィンが敵の初撃を受け、アイラが仕留める、そんな連携が多くあった。二人はお互いに気遣いながら、自分の任務にあたった。
ラケシスを救うために進軍を始めたシグルド達だったが、襲い来る敵を迎撃し、戦火を掻いくぐるうち、どんどんとアグストリア深くに入り込み、アグストリアの民から見れば、それは侵攻の様相を呈していた。
シグルド達が王都アグスティについた頃には、グランベルの役人が各地の城に派遣され、アグストリアがまるでグランベルの属国のようになっていた。ついにアグスティを制圧したシグルドは、戦場からシャガール王を助けだしたエルトシャンと相まみえた。
アグストリア各地を制圧され憤るエルトシャンに、自分も戸惑っていることを話したシグルドは、「一年待ってほしい」、そう伝えるのだった。
◆◆◆
一年……。政治的、戦略的には心血を注ぎバーハラと交渉を重ねなければならなかったが、戦術的、現場レベルにおいては、期限付きとはいえ休戦状態であることに変わりはなかった。十分厄介な状況であったが、明るい話題もあった。シグルドとディアドラの間に嫡子が生まれたのだ。その愛らしい姿に、騎士たちも笑顔になった。
彼らは気付いたらアグスティに駐留していた。何のための戦いなのかわからないまま戦って、戦って……。やるせない気持ちと裏腹に、戦いとその思いを共有してきた戦士たちの絆は、自然と深まって、まさに戦友であった。
アグスティでの生活は、自然とエバンスで過ごした日々を思い出させた。時が来るまで、訓練を欠かさず、できることをする。それぞれの戦士たちができるのはそこまでだ。
その日の朝、騎馬兵の合同訓練が終わったころ。キュアンはフィンを城下町に誘った。グランベル軍はアグストリアの民にしてみれば突然の侵略者であり、歓迎されていない。二人は悪目立ちしないよう、アグストリア風の服に着替えてから街に出た。
天気は何の因果にも繋がれず、よく晴れて、気持ちの良い風が吹いていた。政治家が策をひねっていても、軍が駐留していても、街はそれなりに賑やかで民の暮らしは穏やかにみえた。
露店の並ぶ通りを歩きながら、キュアンは言った。
「フィン」
「はい」
「どこか、体の具合が悪いか?」
「え?いえ、どこも悪くありません」
「……そうか、それならいい」
キュアンが露店で足を止める。
「ん?これは、エスリンに似合いそうだ」
フィンも立ち止まってキュアンを目で追うと、その先に色とりどりのショールが沢山並んでいた。キュアンは淡い色の、柔らかくて透けるような素材のショールを手に取った。
「フィン、どう思う?」
「そう、ですね。エスリン様にお似合いになると思います」
突然意見を聞かれて、たどたどしく返事をするフィン。
キュアンは、ははっと声を出して笑って、困ったような顔をした。
「……セリスが生まれただろう?可愛いよ、シグルドにもディアドラにもよく似ている」
フィンは黙って頷いた。
「……エスリンは多分、いや多分じゃないな。当たり前の話だ。エスリンはアルテナに会いたいんじゃないかと思うんだ。そりゃあ今までも会いたかっただろう、でも殊更に会いたくなっているんじゃないかと思う」
状況が状況だ。各国の協議の書簡が世界中を行きかっている。そしてマディノには、アグスティ奪還を虎視眈々狙っているかもしれないシャガールがいる。今、この時は、まだ動くことができないのだ。
「せめて少しでも、何か、慰めになればと思ってな」
キュアンは自分の下がった眉を撫で、ばつが悪そうに笑った。フィンは黙って頷いた。
「自分ではあまりお役に立てないかもしれませんが、何か素敵なものを探しましょう」
キュアンは頭をかいて、若い騎士に「今日は、頼む」とこぼした。
二人は露店をめぐる。アクセサリー屋、本屋、服屋、お菓子屋、雑貨屋……。どれがいいか悩んでいるうちに、すっかり昼時が過ぎてしまいそうになり、情報整理の時間も兼ねて二人は食堂に入ることにした。
「悩むなあ!ははっ」
食後の紅茶を飲みながら、キュアンは少し豪快に笑った。
「キュアン様でも、悩まれるものなのですね」
「そりゃあ悩むよ。エスリンに贈り物をするときは、特に、毎回とても悩む」
紅茶を一口飲んで。
「喜んでほしい。笑顔が見たい。……もちろん泣き顔も、怒った顔も全部私のものだけど、やっぱり笑顔は特別だ。喜ばせてあげたいんだ」
キュアンが窓の外を見て呟いた。フィンも紅茶を一口……。
そうだな、例えばアイラなら、何を贈ったら喜ぶだろう。
訓練服を縫ってくれたお礼……、
あまりに見え透いた口実だな……。
「フィンには居ないのか、喜ばせたい女性は」
突然の話題に、フィンはむせた。キュアンは驚いた顔をした後、口元に手を寄せて笑った。
「ふふ……。その反応は?」
「ごほっ、ごほっ……そんなことを急におっしゃるからです……!」
「ふぅん?喜ばせたい女性がいるんだな」
「キュアン様!」
フィンは珍しく少し大きい声で主君の名を呼んだ。否定はしなかった。自分の気持ちを否定するような気持ちがしたのだろうか。
ははっ、とキュアンは笑って紅茶を飲み干すと、二人は店を出て、贈り物選びに戻った。
食堂を出たキュアンは、斜向かいの店に視線を向けた。アクセサリー屋だ。アクセサリーを扱う露店は何件もあるが、その店は露店らしからぬ雅やかで上品な感じがした。二人はそれぞれに手に取って、品物を確かめていく。
「これは……」
フィンは鍵で開閉する飾りのついたペンダントを見つけた。小さな鍵を差し込んで回すと、ぱかっと開いた。家族の肖像やお薬を入れる方が多いですよ、と店主が言った。
鍵で開く部分は丸型、菱形などいろんな形があり、どれも細かい装飾が美しく、中には小さい宝石があしらわれている物もあった。
「へえ、これはいいな!」
キュアンも手に取って、そう言った。帰ったらアルテナの肖像を入れてもいい。私はこれにしよう、フィンはどうする?とキュアンは訊いた。フィンは少し考えて、おずおずとキュアンに尋ねた。
「……急にアクセサリーなどを贈っては、かえって負担になったり、しませんでしょうか」
「そうだな。うーん……」
キュアンは茶化すでもなく、まるで兄のようにふわっとした笑みを見せてから、真剣に一緒に悩んでくれた。ほんの少し照れくさそうに、私が最初にあげたのは花だったかな、と呟いた。
「……でも、彼女なら。アクセサリーでも喜ぶと思うけどな」
フィンがぴくっとする。自分の頭の中に思い描いた人が筒抜けになったようで、顔が一瞬で熱くなった。フィンは目をつぶって、眉間にしわを作った。
◆◆◆
結局、フィンはキュアンと同じ店で開閉式のペンダントを買った。キュアンが購入したものとは異なるデザインの、深い海の色のような、小さい宝石のついた楕円形のペンダント。
買ったものの、いざ渡そうと思うと自信がなくなってしまい数日が経った。多分、渡せないのだろう、フィン自身そう思っていた。渡す日が来るとは思っていなかった。
◆◆◆
その日は突然やってきた。
シグルドとエルトシャンとの約束から半年。一年を待たずにマディノ城のシャガールが兵力を整え、王都アグスティ奪還のために進軍してきたのである。グランベル、バーハラからの下命は、アグスティの死守だった。
民衆に敵とみなされ居心地は良くないとはいえ、平時を過ごしていたアグスティのシグルド軍は、俄かに慌ただしくなった。地理の確認、周辺民家や賊の状況把握、武器庫からの運搬、食料の調達……。普段から備えはしているとはいえ、戦闘前はやることは沢山ある。軍の全員がそれぞれの役割をこなしていく。
馬の確認を終えたフィンの脳裏に、漠然とした不安がよぎった。シャガールが挙兵するとなると、エルトシャン率いるクロスナイツが出兵してくる可能性が高いのではないか。キュアンから彼の持つ神器ミストルティンについて訊かされていたフィンは、最前線に立つことが多いアイラが心配になった。居てもたってもいられず、戦準備の喧騒の中、アイラが担当していた武器庫に向かって駆け出していた。
◇◇◇
「アイラ!」
私は武器庫のドアを開けるなり、殆ど叫んでいた。在庫の最終確認をしていたアイラは、びくっと肩を揺らして振り返った。
「フィン!?敵襲か!?」
武器庫にはアイラしか居なかった。私は息を切らしたまま、緊張と不安といろいろな感情が混ざりあった結果、少し俯き加減でアイラに歩み寄った。アイラは少し後ずさりした。少し怖がらせているのかもしれない。
構うものか。戦闘が始まる前に伝えたいことがある。私は彼女に近づいて、そして彼女の首に腕を回した。
「な……」
か細い声が聞こえる。私は腕を彼女から離して、一歩下がって声を絞り出す。
彼女の顔を見ることができない。
「どうか、あなたに……聖戦士の御加護がありますように」
彼女は自然と胸元に手を運ぶ。しゃらと金属の音がして、彼女はペンダントを掬った。息をのむような、かすかな音がした。私はようやく顔を上げ、彼女の瞳を見ながらゆっくりと伝えた。
「お守り代わりです。シャガール王の下には、まだエルトシャン殿のクロスナイツが居ます。アイラ。どうか、無事でいてください」
アイラはペンダントを握りしめた。今度はもう一度手のひらを開けて、ペンダントを見ている。
「……ありがとう、フィン。あなたもどうか、どうか無事で」
そう呟いて、ペンダントを自分の唇に寄せた。
「あっ……」
思わず声が出てしまって、恥ずかしかった。私の声を聴いて、彼女の頬は少しだけ上気した。
「……お守り代わりだ」
照れ隠しなのか、本心なのかわからない言葉で、私の中の様々な思いが溢れてしまった。私は衝動に抗わず、抗えず、彼女を抱きしめた。彼女は私の胸に頬を擦るようにして、抱きしめ返してくれた。
「無事でいて、フィン」
「アイラも、無事で。……私は、あなたが……」
私は言葉を飲み込んだ。今言うべきではない気がした。彼女の頭を撫でて、彼女の匂いで胸をいっぱいにして。
「……あなたに……。生きていてほしいんです」
「生きていたら、生き延びたら……」
「はい、きっと。先ほどの続きを、お伝えします」
「……わかった。きっとだ」
アイラはそう言って顔を上げて、私を見つめてくる。
「もし、聴けなければ……。私は、困る……」
私でも直感的にわかる。いろんな感情をはらんだ、艶めかしく潤んだ瞳。
「……それは、私たちの掟に反しますね。必ず生きて、お伝えします」
◆◆◆
シグルド軍はエルトシャン率いるクロスナイツ、シャガール王を撃破。マディノ、シルベールを制圧し、混乱に乗じて動き出した海賊の居城オーガヒルも制圧した。戦闘が終了し、すぐさまシグルドは全員を集めて全員の安否を確認した。群衆の中で、フィンとアイラはお互いを見つけて、安堵の表情を浮かべた。
そんな中、シレジアの天馬騎士がシグルドの元を訪れ、事態が急転していることを知らせる。グランベルのとある諸侯の陰謀により反逆者となったシグルドは、慌ただしく中立国シレジアに逃れることになった。天馬騎士たちの導きにより、一行はシレジアのセイレーン城にたどり着いた。
◆◆◆
フィンはその夜、約束を果たすためアイラの部屋を訪ねた。
招き入れられ、ドアを閉めてすぐ。無事を確かめる様に互いに抱きしめあった。
戦時の装備を解いたアイラの肩は、想像以上に細くて、触れあう全てが柔らかくて熱かった。
「無事でよかった……、アイラ……」
「お守りのおかげだ、ありがとう、フィン……」
約束の言葉を伝えようとして、フィンは耳元に唇を寄せた。言葉にする前の息がアイラの耳元をくすぐったようで、彼女は少し身をよじって小さく吐息を漏らした。恥じらっているのか期待しているのか、いつも見せない彼女の初めてみる表情や仕草が、どうしようもなくフィンをそそった。
フィンは言おうとした言葉を一旦しまった。意地が悪いと思いつつ、衝動を止めることができなかった。いつも見られないアイラの姿を、もう少し見ていたい気持ちになってしまったのだ。
彼女の耳元で。言おうか、やめようか、どうしようか……。アイラにはその息遣いだけが伝わった。
「……っ」
アイラはたまらなくなってもう一度身をよじり、フィンの腕の中で俯いた。これ以上、思わせぶりなことをされては身が持たない。そう思ったのだ。
「……困っていますか?アイラ……」
フィンの声色は優しいのに、息遣いは裏腹で、煽情的だった。
「困っている。……とても……」
俯いたままのアイラは、少し震えた吐息交じりの声を出す。
「……あなたの困りごとは、私が全部、聴いて差し上げることになっているのです。何に困っているのですか?……このフィンに、教えてください……」
アイラは美しい瞳をフィンに向けた。潤んだ瞳が全てを伝えている。フィンはその瞳を優しく見つめた。複雑な思いは殆ど余すことなく、フィンに伝わっていた。しかしフィンは、アイラの口から聴くまで、続きを話すつもりはないらしい。
アイラは恥ずかしさでいっぱいで、でもこんな風にされていることに少しの嬉しさがあって、そんな自分に戸惑いもあって。フィンを見つめたまま、自分の困りごとを言おうと試みる。
「……続きを、……っ!」
自分でも想像できないくらい艶めいた声が出て、アイラはより一層顔を赤らめた。
「続きを……?」
「あの時の、続きを、聴かせて……」
フィンはアイラの答えに満足したように、優しい笑みをこぼして。
「……私は、あなたが好きです。アイラ……」
そう言って。瞳を閉じた愛しい彼女に、口づけを落とした。
◆◆◆
セイレーンでの暮らし。政治的なことはシグルドたちに最早できることはなく、シレジアの王妃ラーナに頼るしかなかった。しかし、その暮らし自体は穏やかで平和なものだった。
フィンとアイラもそうだった。二人で武器を交え、言葉をかわし、肌を重ね……。隠遁生活とはいえ、こんな日々が続くのも悪くないと思うほどだった。こんなに幸せな時間が、たとえ束の間でも与えてもらえるなんて。イザークがグランベル領になっている今、幸せだと声を大にしては言えないけれど、アイラは毎日が幸せだった。
◆◆◆
落ち延びた日から数か月たったある日。冷えこむようになってきた早朝の談話室で、アイラはエスリンと一緒になった。エスリンはいつも通りにこやかだった。
「あら、アイラ。早いのね」
「エスリン様!今日は早く目が覚めてしまって。この部屋の掃除でもしようかと思ったのだが……先を越されてしまったようですね」
「私もね、今日はなんだか早く目が覚めちゃって。……ふふ」
不意にエスリンが笑うので、アイラは不思議に思った。エスリンはアイラの近くまで寄ってきて。
「……なんだかフィンに似てる時があるの、話し方。ふふっ」
「え、エスリン様!」
アイラとフィンが恋仲であることは、すでに軍の誰しもが知っていた。仲睦まじい爽やかな若い二人が並んで歩いているのを、城のみんなが見守っていた。二人もそれには気づいていて、気恥ずかしくもあり、嬉しくもあった。
それはそれとして。アイラには、気がかりなことがあった。今、ここには二人しかいない、打ち明けるなら、今しかないのかもしれない。
「エスリン様、その……」
アイラは声を潜めてエスリンに話しかけた。エスリンは嬉しそうに耳を傾ける。
「レンスターへ戻られるのか?」
「えっ?」
エスリンは小さく声を上げた。アイラは首を振った。
「……いや……。そうだな、どこから話せばよいのか……」
エスリンはソファーに座るように促した。アイラは小声で話を続けた。
「……エスリン様、子ができたのでは?」
エスリンは驚いた。
「まだキュアンにしか伝えてないの。どうしてわかったの?」
「……なんとなく……。ただの勘だ……。最近、よく当たる気がする」
そういって自分のお腹に手を当てた。エスリンは息をのんだ。そうだったのね、と眉を下げて頷いた。
「まだ確証がなくて、フィンにもまだ……」
エスリンは、母の微笑みをアイラに向けて、
「私にできることなら、何でも言ってね」
と、アイラの手を握った。
「では、一つ頼みたい。レンスターに戻るときに、フィンを。連れて行ってほしい」
エスリンは驚いて心配そうに言う。私たちはレンスターに戻って、正規軍の準備を整えた後に再びここに合流するのだから、フィンが望むならセイレーンに残すつもりだと伝えた。
アイラは話を続けた。
「……エスリン様……。どうか罪深い私の、お伽話を聞いてくれないだろうか」
アイラは懇願した。エスリンは頷いて手を握り直し、話を聞いた。
この後、シグルド軍は反逆者として滅ぶのでは、ということ。 私も共に散るのでは、ということ。
だから、フィンはレンスターに帰っていてほしい。生きてほしいんだ、とアイラは言った。もし生きてさえいれば。例えば今私が、もし妊娠していたとして。この後シレジアで子を産んだとしたら。フィンがレンスターで生きていれば、私が死んでも、いつか子と巡り合うことができるかもしれない。
エスリンはなかなか言葉を探せずにいた。
「ではアイラも一緒に、レンスターへ行きましょう?イザーク王族だとわかれば、処刑されてしまうかもしれないわ」
「それはできない、私はイザークの戦士だから。シグルド殿には恩がある。それには報いなければならない。先ほどの話も、趣味の悪い、想像の話にすぎない」
エスリンには、アイラを説得する言葉を探すことができなかった。
◆◆◆
シレジアの寒さは徐々に厳しさを増し、雪の降る季節となった。エスリンのお腹は目立たないものの、安定期を迎えたようだ。アイラだけに、とエスリンが教えてくれた。
◆◆◆
その夜。
フィンは、アイラの部屋を訪ねた。ノックをしても返事がない。フィンはドアを開け、部屋の中を見渡した。アイラは窓際に立ち、冬のシレジアの星空を見ていた。
「アイラ……?」
小さく呼びかけるが、アイラの返事はない。フィンは窓辺に向かい、隣に寄り添った。
「アイラ……私は、レンスターに一度戻ることになりました」
アイラは声を出さず、小さく頷いた。
「キュアン様はレンスター軍を率いて、再度合流するおつもりです」
「……それが良いと思う。援軍は心強い。……そしてキュアン殿には、あなたが必要だ」
淡々とアイラは言った。悲しみを全面に出すわけでもない彼女をみて、フィンは少しだけ戸惑っているように見えた。
「……忘れたか?私はこれでも、一国の王女だったんだ」
夜空を見上げていた瞳は、フィンを映して、
「信頼できる有能な人材は、腹心として傍に置きたい。そういうものだ」
唇は優しく笑みを浮かべた。
「準備ができたら、必ず参ります」
フィンが思いを込めて言う。アイラは微笑んだ後、俯いてしまった。
「……あなたが生きていてくれないと、困る……」
そう、声を絞り出した。
「あなたを困らせては、私たちの掟に反しますね。……大丈夫、必ず生き延びます」
フィンは俯いたままのアイラを後ろから抱きしめた。抱きしめたまま彼女の首に掛かっている、かつて自分が贈ったペンダントを開いて、ほんの少し束ねた自分の青い髪を入れた。
「アイラ。私は暫くお傍を離れます。私だと思っていただくには、少し、小さすぎるかもしれませんが……」
そう言って、フィンは蓋を締め、鍵を掛けた。
彼の言葉が耳元をくすぐるたび、
過ごした濃密な時間が思い出されて。
初めて好きだと言ってもらったこの部屋で。
アイラの我慢は限界を超え、
深い色の瞳から、ひとしずくの涙が零れた。





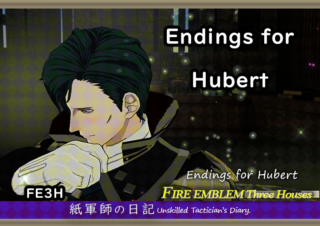
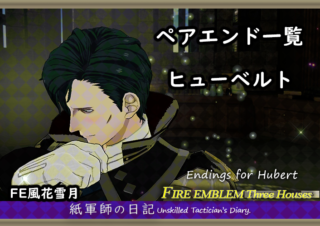




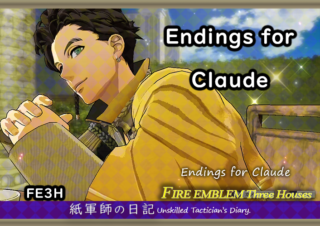


コメント